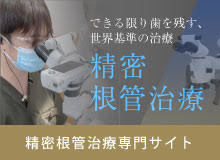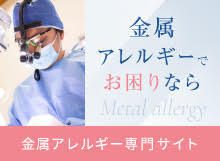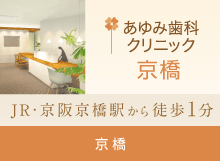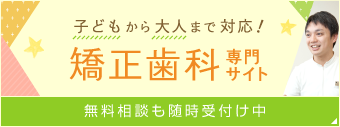歯科豆知識
高齢者は要注意!噛む力と認知機能の深い関係を歯科医が解説


「最近、噛みにくくなった」「食事が以前より遅くなった気がする」──こうした変化は、年齢とともに誰にでも起こりうるものです。しかし、実はこうした噛む力の低下が、思わぬところに影響を及ぼしているかもしれません。
近年の研究では、噛む力と**認知機能(脳の働き)**との密接な関係が注目されています。特に高齢者にとって、噛む力の衰えがそのまま認知症のリスクにつながる可能性があることがわかってきたのです。
この記事では、歯科医の視点から、「噛む力」と「脳の健康」の関係について詳しく解説します。あわせて、日常生活でできる口腔ケアや噛む力を保つための実践方法も紹介していきます。
噛む力が脳に与える影響とは?
食事中、私たちは自然と噛むという行為を繰り返していますが、この動作は単なる咀嚼(そしゃく)以上の役割を果たしています。
食べ物を噛むことで、脳の記憶を司る「海馬」や、思考・判断を担う「前頭前野」などが刺激されます。この刺激によって脳内の血流が促進され、神経の働きが活発になるとされています。
つまり、よく噛むという日常の動作が、脳を健やかに保つトレーニングになっているのです。
噛む力が弱まると認知機能も低下する?
東京医科歯科大学の研究では、奥歯でしっかり噛めない高齢者ほど、記憶力や判断力が衰えやすい傾向にあることが明らかになりました。
また、歯を失ったまま義歯などを使わずに放置している人では、脳の前頭葉や海馬の萎縮が進行しやすいという報告もあります。
さらに、日本老年医学会の調査では、残っている歯の本数が少ない人ほど認知症の発症率が高くなるというデータが示されました。特に、10本以下しか歯が残っていない人では、そのリスクが2倍近くに上るとされています。
このように、噛む力の低下は、脳の健康と密接に結びついているのです。
歯を失うと起こる心と体への影響
噛む力が落ちることで生じるのは、脳への刺激の減少だけではありません。以下のような影響が日常生活に広がることがあります。
-
食事内容の偏り:柔らかいものばかりを選ぶようになり、野菜やたんぱく質が不足しやすくなります。
-
栄養不足と筋力低下:十分に栄養が摂れなくなることで、体力や免疫力の低下につながる恐れがあります。
-
会話や外出の減少:うまく噛めない・話しづらいと感じることで、人との交流を避けがちになり、孤立や抑うつ状態になることもあります。
こうした負のスパイラルは、認知症を進行させる一因にもなりかねません。
高齢者にこそ必要な“噛む力を守るケア”
噛む力を維持し、脳を元気に保つためには、日々のちょっとした心がけが大切です。以下の対策は、どれもすぐに実践できるものです。
-
歯科医院での定期チェック
虫歯や歯周病を早期に発見・治療することで、歯の寿命を延ばすことができます。入れ歯の調整も忘れずに行いましょう。 -
義歯やインプラントの活用
歯を失った場合は、そのままにせず咀嚼機能を回復させる治療を選びましょう。「噛める状態」に戻すことが、脳への刺激を取り戻すカギになります。 -
噛みごたえのある食材を意識する
ごぼう、れんこん、りんごなど、噛み応えのある食材を少しずつ食事に取り入れることで、自然と噛む回数が増えます。 -
口腔体操で筋肉を鍛える
「パタカラ体操」や「口すぼめ・舌出し運動」などの口腔機能トレーニングを取り入れることで、噛む力や話す力の維持に効果的です。
まとめ|噛む力を大切にすることが、脳を守る第一歩
高齢になるにつれ、歯を失ったり、噛む力が衰えたりするのは自然なことかもしれません。
しかし、そこから先の対応によって、脳の健康状態や生活の質に大きな差が生まれます。
「しっかり噛める」ことは、食事の楽しみだけでなく、記憶や思考を支える大切な生活機能です。
認知症を遠ざけるためにも、今日から“噛む力”に意識を向けてみましょう。歯科医院でのケアと、ご自宅での小さな工夫が、未来のあなたの脳を守ってくれます。
医療法人隆歩会 あゆみ歯科クリニック京田辺同志社山手 院長 小木曽 新
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
| 午後 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
午前:9:00~13:00
午後:14:00~18:00
※祝日がある週の木曜日は診療しております。
休診日:木曜・日曜・祝日