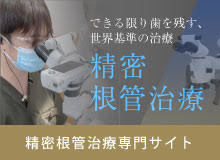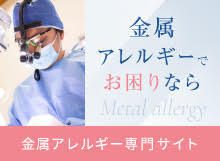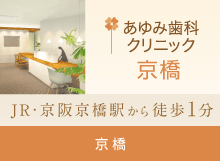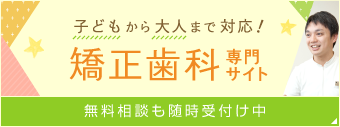歯科豆知識
【歯医者が教える】虫歯になりやすい人の特徴と今日からできる予防法


こんにちは。京田辺市・精華町のあゆみ歯科クリニック京田辺同志社山手の院長、小木曽です。「毎日しっかり歯を磨いているのに、なぜか虫歯ができる…」このような悩みを抱えている人は少なくありません。
実は、虫歯の発生には 遺伝的要因だけでなく、生活習慣や口内環境が大きく関わっている のです。
この記事では、虫歯ができやすい人の特徴やそのメカニズム、今日からできる効果的な対策 を詳しく解説します。
「自分は大丈夫?」と思った方は、ぜひチェックしてみてください。
なぜ虫歯ができるの?その仕組みを理解しよう
虫歯は、ミュータンス菌などの細菌が食べ物の糖分を分解し、酸を作り出すことで歯が溶かされる(脱灰する)現象 です。
通常、唾液には 歯を修復する「再石灰化」作用 がありますが、口内環境が悪化するとこのバランスが崩れ、虫歯が進行してしまいます。
特に、口の中が酸性に傾く時間が長いほど、歯のエナメル質がダメージを受けやすくなる ため、生活習慣の改善が重要になります。
虫歯になりやすい人に共通する5つの特徴
1. 唾液の分泌量が少なく、口の中が乾燥しがち
唾液は、食べカスや細菌を洗い流し、酸性に傾いた口内を中和する重要な役割 を果たします。
しかし、何らかの理由で唾液の分泌が減ると、虫歯のリスクが一気に上昇します。
唾液の量が減る原因には以下のようなものがあります。
✔ 口呼吸の癖がある(睡眠時に口が開いてしまう人は要注意)
✔ 緊張やストレスが多い(交感神経が活発になると唾液が減少)
✔ 加齢や服用中の薬の影響(抗うつ薬や抗アレルギー薬などが影響することも)
唾液の分泌を促すためには、水分補給をこまめに行う、ガムを噛む、唾液腺をマッサージする などの工夫が効果的です。
2. 間食の回数が多く、口の中が常に酸性になっている
食事のたびに、口の中は一時的に酸性になりますが、時間が経つと唾液の働きで中和され、歯の修復(再石灰化)が進みます。
しかし、間食が多い人は口の中が酸性に傾く時間が長くなり、歯の表面が溶け続ける ことになります。
特に以下のような食習慣は虫歯の原因になりやすいです。
× 仕事中や勉強中に 少しずつジュースやコーヒーを飲み続ける
× お菓子を頻繁につまむ(特にキャラメルやグミなど粘着性の高いもの)
× 夜遅くに甘いものを食べ、そのまま寝てしまう
間食をする場合は 時間を決めて食べる、食後は水やお茶を飲んで口の中をすすぐ などの対策を取りましょう。
3. 歯並びが悪く、歯磨きが十分に行き届かない
歯並びが悪いと、ブラシが届きにくい部分にプラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。特に歯が重なっている箇所や奥歯の溝には磨き残しが多くなりがち です。
また、噛み合わせのズレによって 一部の歯に強い負担がかかると、エナメル質が摩耗し、虫歯が進行しやすくなる こともあります。
矯正治療を受けることで、歯磨きのしやすさが向上し、虫歯や歯周病のリスクを大幅に減らすことが可能 です。
4. 甘いものや酸性の飲み物を頻繁に摂取している
砂糖は、ミュータンス菌の活動を活発にし、酸の産生を増やす ため、虫歯の大きな原因になります。
また、酸性の飲み物(炭酸飲料、スポーツドリンク、果汁ジュース、ワインなど)は エナメル質を直接溶かす働き を持つため、過剰摂取は避けたほうがよいでしょう。
甘いものを食べるときは 食後に摂る、ストローを使って歯に直接当たるのを防ぐ、水で口をすすぐ などの工夫をすると良いでしょう。
5. 家族に虫歯が多く、生活習慣が似ている
虫歯菌は 親から子へと感染することがある ため、家族に虫歯が多い場合、同じ環境で育った子どもも虫歯になりやすい傾向があります。
また、家庭での 食事習慣やオーラルケアの習慣 も影響を与えるため、家族全員で口腔ケアに取り組むことが大切です。
虫歯予防のために今日からできること
・よく噛んで食べ、唾液の分泌を促進する(キシリトールガムを活用するのもおすすめ)
・食事の時間を決めて、間食を減らす(特に夜間の飲食は注意!)
・歯磨きはフッ素入りの歯磨き粉を使い、フロスや歯間ブラシを併用する
・歯科医院で定期的に検診を受け、専門的なクリーニングやフッ素塗布を受ける
まとめ|虫歯は日々の習慣を見直すことで予防できる!
虫歯になりやすい人には、唾液の分泌量、食習慣、歯磨きの精度、家族の影響などの共通する要因 があります。
しかし、これらを意識し、適切なケアを続けることで 虫歯のリスクを大幅に減らすことが可能 です。
今日からできる予防策を取り入れ、健康な歯を維持する習慣を身につけましょう!
医療法人隆歩会 あゆみ歯科クリニック京田辺同志社山手 院長 小木曽 新
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
| 午後 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
午前:9:00~13:00
午後:14:00~18:00
※祝日がある週の木曜日は診療しております。
休診日:木曜・日曜・祝日